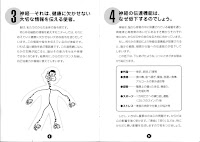このところの足の衰えはこの間も書いた通りだ。ヨチヨチとした前のめりの歩きぶりは自分のみならず周囲も認めるところとなった。ついこの間、一ヶ月に一、二度は行く西荻窪の居酒屋のお姉さんから「今日は珍しく酔ってますね」と言われる。何のことはない。足がよろけていたのだ。一ヶ月前まではそうは見えなかったのだ。秋にはひょいと登れたカウンターバーの高いスツールにも座れず、一緒に行った職場のスタッフとバーテンさんとに手助けしてもらって這い登った。酔っぱらっていたとは言え、平らな所で転んで起き上がれず、通りがかりの若い男の子に助け起こしてもらった。(酒飲みがらみの話ばかりだなあ~情けない限りだ)
ただの酔っ払い話だと思って、親しい友人達は「まったく恥ずかしいわね~」と呆れる。姪も「ここんとこ急だよね!」と衰えぶりに驚く。そうだよなあ、老化にしては早いし、寝たきりにしている訳ではないのに、と考えている内に足の震えが始まった。ネットで調べたり、素人考えで、「パーキンソン病」「リュウマチ」「脳梗塞の後遺症」等々を疑う。気が付かない内に小さい脳梗塞はおきていると聞いたことがある。
そんな中、久しぶりに会った少し年上の友人Sさんが、私の様子を見つつ話の内容を聞いて「私の病気の初期症状にそっくり」と、言う。「繊維筋痛症」と、初めて聞く病気だ。世の中には本当に色々な病気があるものだ。いわゆる難病の一つで、日本人には少なく、あのレディ・ガガも闘病中であるという。(だから何?なのだけど…)
鬱病が併発していることが多いそうで、 症状が進むとガラスの破片が身体中を流れるような激痛や、止まらない震え、疲労感に悩まされるという。恐ろしい! 弱虫の私には耐えられようもない。そうならない内に対処しないといけない。西洋医学では難病とされ、これと言った治療法もなく、痛み止めの薬も副作用が酷く、彼女も余計に具合が悪くなったそうだ。痛み止めは痛みをごまかすだけで根本の治療にはならない。
私は以前、入院したことをきっかけに、西洋医学の矛盾と薬の怖さを身をもって知り、退院後は抗生物質で弱った身体を回復させるために、東洋医学、自然療法のそれこそありとあらゆるものを試した。漢方薬、サプリメント、熱いもの(灸)から冷たいもの(-160℃の水素ガス)、リフレクソロジー、カイロプラクティック、ヒーリング、痛いものから無痛のもの、etc. これらの療法の理念は共通している。薬や化学的な物に頼らず、人間が本来持っている自己治癒力を高めて自分の力で病気を治すというものだ。その為の方法が違うだけで、どれもそれぞれに素晴らしい。3年程のジプシーの結果、私がたどり着いたのは仙骨療法だった。無痛、瞬間で仙骨だけを調整するというシンプルなやり方、考え方が気に入り、勿論、身体の調子が良くなったからだが、以来30年近く続いている。その間、病院へ行ったのは3回程か…、薬もほとんど飲んでいない(というか、強い薬は吐いてしまうようになった)。それなのに…
今回の不調は、健康過信とストレス過剰が招いた結果に他ならない。
繊維筋痛症のことを教えてくれたSさんも、この病気は「原因はストレスでしかない」と言う。医師も「身体の鬱病」と言ったそうである。私の場合は、精神的なものより物理的なストレス(休まない)なので、休めば良いことである。2年前の唾石症騒ぎの折にも、休むと宣言したのに三日坊主に終わったので、職場のスタッフは私を「オオカミ少年」扱いだ。でも、今度こそ休むぞ! こんなに不調じゃ仕事の効率も悪いし、元気になって頑張ればいいものね!(って、リキむなってば)
さて、難病で苦しんだSさんがたどり着いたのは、やはり自然療法のMTSという療法だ。これもカイロプラクティックを原点とした療法で、神経の伝達機能が阻害された結果が病気を生むという理論で、その機能を高める治療である。治療も短時間で無痛だと言う。主宰のU先生に診てもらいたいという患者は引きも切らず、予約もびっしり、さらにU先生は高齢ということもあって新規の患者は診ないというところを、Sさんが私の為に頼み込んでくれ予約を取ってくれた。有り難いことだ。1回目の治療後から歩幅が大きくなったような気がする。「筋肉があるから心配ない。脳からの神経伝達さえ治せばいくらでも歩ける。」とのことで、心から安心した。柔和な笑顔のU先生から「大丈夫」と言ってもらっただけで、元気が出る。施術者の人間性と患者との相性は大切だ。週1回、連続3回は続けた方が良く、私程度の症状だと後は時々で良いだろうということ。楽しみだ。
病院へ行ってないので繊維筋痛症と特定された訳ではないが、こういった種類の病気にはストレス軽減と共に筋肉を動かすリハビリが重要だと言う。思えば昨秋から足の衰えを感じ、運動不足とばかり思い、ラジオ体操を始めた。やっていなかったらどうなってしまっただろうと思う。身体を守ろうという潜在意識が働いたのだろう。ラジオ体操を始めてそろそろ半年だ。とにかく続けてみよう。
2018年3月22日
2018年3月12日
2018年3月2日
169 運動再開 / ラジオ体操にヨガ
そろそろ本気で身体を動かさなければいけないと思っていた。
街を歩くと、道路に写る影法師やビルのガラスの街鏡に、ヨタヨタとした情けない我が姿が映る。身体の衰えを自覚せざるを得ない。運動の必要性を実感していたのだ。
年齢もあり、以前のようにスポーツクラブへ行って激しい運動をする気はない私に周りがこぞって勧めたのが、C....Sとかいう高齢女性向けの、格安で月に何度でも行けて、適度な運動をするクラブだった。妹二人、叔母もそれぞれ長野県のクラブに通っていて効果の程を熱心に話す。友人の母親(90歳過ぎ)も、私にどうかと勧める。それではと住まいの近くを捜すと西早稲田と初台にあったので、乗換え無しで行ける西早稲田へ下見に出かけた。
スーパーマーケットの上にあるそのクラブには、お年頃のお姉さまたちが沢山集まって楽しそうに体を動かしている。スタッフの女性たちはお客さんを「何々子さん」とか「ナニナニエさん」とかファーストネームで呼ぶ。ロッカーも無く、代わりに荷物置きとしてカラーボックスが幾つか並べられている。お客さんへのお知らせは画用紙にカラーペンや色紙を使って貼り出している。何処かで見た光景だ。そう、母が入っている特養なのだ。私は、シャワーが無い理由や、ファーストネームで呼ぶ理由を聞いたりして、もうすっかり意気消沈して、その(老人ホーム)クラブを後にした。
帰路つらつら考えながら、商売上手だなあと感心しきりだった。これから高齢女性は増えるし、ターゲットにしたのはまず正解だ。会員もスタッフも女性だけなのも高齢女性の心理をついている。クズレ気味の身体に汗かきかき、イケメンにコーチされたくないものね。会場も、青山とか渋谷のお洒落な場所に無いのが気楽。(西早稲田や初台の人ごめんなさい!)設備投資も少なくて済む。店舗は地方に多く、何百という日本一の数を誇るのも頷ける。
ここで色々言ったところで、「お前もそういう歳だろう!」と言われるのが関の山だ。でも、楽しみに通えないような所には行きたくないのだ。
そうこうする内に、昨年の秋、アコーディオニストの後藤ミホコさんから良い話を聞いて、ラジオ体操を始めた。10キロ以上の重い楽器を弾きこなすミホコさんの身体はほっそりしながらしなやかで、ずっと何年も体形も変わらず、食べることが好きなので我慢せずぱくぱくと気持ちよく食べる健啖家でもある。代謝の良い身体とはこういうことかと目の当たりにしている。以前から感心していたのだが、やはりそういう人は身体に気をつけていて、努力をしていたのだ。かといって激しい運動をする訳でもなく、やっているのは毎日のラジオ体操と週一のヨガだという。ラジオ体操を始めたきっかけは、彼女のラジオ番組のスポンサーでもあり関西での親しい交友関係にある、大阪の腰痛館というクリニックのヒロ先生の勧めだったそうだ。
「一日に3分ぐらい時間を取れないはずはない」「まず三ケ月やれば何かが変わる」とヒロ先生はおっしゃったそうだ。改めてそう聞くまで、ラジオ体操を大層なもののような気がして重い腰を上げられなかった私も早速始めたのだった。10月だったので、三ケ月やれば丁度年末だし区切りもも良いなと、ヒロ先生のこの二つの言葉をおまじないにしてやってみた。旅行中も続けられたし、休んだのは3日もなかったろうか…
そして、年明けて二ヶ月続けて3月に入った。今月末で半年間続けたことになる。半年!これを同じ時間続ければ、1年だ。時の過ぎるのは早く、過ぎてしまった半年や一年を振り返る時、もう…、とネガティヴな気持ちになりがちだが、何か具体的な行動の毎日の積み重ねの結果だと思うと、その時間の長さに充足を覚えることに気がついたのだった。もう30年もラジオ体操を続けているんですよ、なんて自慢になるよね。(そんなに生きる気か!?)
もう一つ、やりたかったヨガだが、近所に良い教室が見つかった。千駄ヶ谷の緑の中のひっそり隠れ家的一軒家で少人数制だ。シニアミドルコースがあり、そのゆるゆる加減が今の私向きでもある。ヨガも幅広く、行者みたいな人もいるが、私が以前やっていたヨガはストレッチスポーツ系に近かった。この教室はインド系で内面、内部に向かうタイプで、細かい神経が目覚める感覚が気持ち良い。
ヨガもいずれルーティンになれば良いなあと思っている。そうなった時に、積み重ね、過ぎた時間が愛おしく思えれば尚のこと幸福だ。
街を歩くと、道路に写る影法師やビルのガラスの街鏡に、ヨタヨタとした情けない我が姿が映る。身体の衰えを自覚せざるを得ない。運動の必要性を実感していたのだ。
年齢もあり、以前のようにスポーツクラブへ行って激しい運動をする気はない私に周りがこぞって勧めたのが、C....Sとかいう高齢女性向けの、格安で月に何度でも行けて、適度な運動をするクラブだった。妹二人、叔母もそれぞれ長野県のクラブに通っていて効果の程を熱心に話す。友人の母親(90歳過ぎ)も、私にどうかと勧める。それではと住まいの近くを捜すと西早稲田と初台にあったので、乗換え無しで行ける西早稲田へ下見に出かけた。
スーパーマーケットの上にあるそのクラブには、お年頃のお姉さまたちが沢山集まって楽しそうに体を動かしている。スタッフの女性たちはお客さんを「何々子さん」とか「ナニナニエさん」とかファーストネームで呼ぶ。ロッカーも無く、代わりに荷物置きとしてカラーボックスが幾つか並べられている。お客さんへのお知らせは画用紙にカラーペンや色紙を使って貼り出している。何処かで見た光景だ。そう、母が入っている特養なのだ。私は、シャワーが無い理由や、ファーストネームで呼ぶ理由を聞いたりして、もうすっかり意気消沈して、その(老人ホーム)クラブを後にした。
帰路つらつら考えながら、商売上手だなあと感心しきりだった。これから高齢女性は増えるし、ターゲットにしたのはまず正解だ。会員もスタッフも女性だけなのも高齢女性の心理をついている。クズレ気味の身体に汗かきかき、イケメンにコーチされたくないものね。会場も、青山とか渋谷のお洒落な場所に無いのが気楽。(西早稲田や初台の人ごめんなさい!)設備投資も少なくて済む。店舗は地方に多く、何百という日本一の数を誇るのも頷ける。
ここで色々言ったところで、「お前もそういう歳だろう!」と言われるのが関の山だ。でも、楽しみに通えないような所には行きたくないのだ。
そうこうする内に、昨年の秋、アコーディオニストの後藤ミホコさんから良い話を聞いて、ラジオ体操を始めた。10キロ以上の重い楽器を弾きこなすミホコさんの身体はほっそりしながらしなやかで、ずっと何年も体形も変わらず、食べることが好きなので我慢せずぱくぱくと気持ちよく食べる健啖家でもある。代謝の良い身体とはこういうことかと目の当たりにしている。以前から感心していたのだが、やはりそういう人は身体に気をつけていて、努力をしていたのだ。かといって激しい運動をする訳でもなく、やっているのは毎日のラジオ体操と週一のヨガだという。ラジオ体操を始めたきっかけは、彼女のラジオ番組のスポンサーでもあり関西での親しい交友関係にある、大阪の腰痛館というクリニックのヒロ先生の勧めだったそうだ。
「一日に3分ぐらい時間を取れないはずはない」「まず三ケ月やれば何かが変わる」とヒロ先生はおっしゃったそうだ。改めてそう聞くまで、ラジオ体操を大層なもののような気がして重い腰を上げられなかった私も早速始めたのだった。10月だったので、三ケ月やれば丁度年末だし区切りもも良いなと、ヒロ先生のこの二つの言葉をおまじないにしてやってみた。旅行中も続けられたし、休んだのは3日もなかったろうか…
そして、年明けて二ヶ月続けて3月に入った。今月末で半年間続けたことになる。半年!これを同じ時間続ければ、1年だ。時の過ぎるのは早く、過ぎてしまった半年や一年を振り返る時、もう…、とネガティヴな気持ちになりがちだが、何か具体的な行動の毎日の積み重ねの結果だと思うと、その時間の長さに充足を覚えることに気がついたのだった。もう30年もラジオ体操を続けているんですよ、なんて自慢になるよね。(そんなに生きる気か!?)
もう一つ、やりたかったヨガだが、近所に良い教室が見つかった。千駄ヶ谷の緑の中のひっそり隠れ家的一軒家で少人数制だ。シニアミドルコースがあり、そのゆるゆる加減が今の私向きでもある。ヨガも幅広く、行者みたいな人もいるが、私が以前やっていたヨガはストレッチスポーツ系に近かった。この教室はインド系で内面、内部に向かうタイプで、細かい神経が目覚める感覚が気持ち良い。
ヨガもいずれルーティンになれば良いなあと思っている。そうなった時に、積み重ね、過ぎた時間が愛おしく思えれば尚のこと幸福だ。
 |
| 緑の中ひっそりと |
登録:
投稿
(
Atom
)